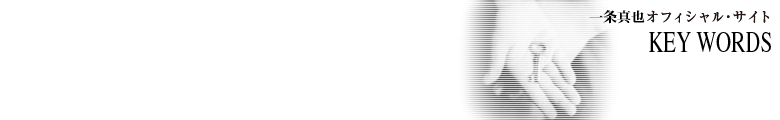一条真也オフィシャル・サイト > キーワード > 唯葬論
唯葬論
拙著のタイトルではありますが、「唯葬論」は単なる書名ではありません。それは、1つの思想なのです。わたしは、葬儀とは人類の存在基盤であり、発展基盤であると思っています。約7万年前に死者を埋葬したとされるネアンデルタール人たちは「他界」の観念を知っていたとされます。世界各地の埋葬が行われた遺跡からは、さまざまな事実が明らかになっています。
「人類の歴史は墓場から始まった」という言葉がありますが、確かに埋葬という行為には人類の本質が隠されているといえるでしょう。それは、古代のピラミッドや古墳を見てもよく理解できます。わたしは人類の文明も文化も、その発展の根底には「死者への想い」があったと考えています。
世の中には「唯物論」「唯心論」をはじめ、岸田秀氏が唱えた「唯幻論」、養老孟司氏が唱えた「唯脳論」などがありますが、わたしは本書で「唯葬論」というものを提唱します。結局、「唯○論」というのは、すべて「世界をどう見るか」という世界観、「人間とは何か」という人間観に関わっています。わたしは、「ホモ・フューネラル」という言葉に表現されるように人間とは「葬儀をするヒト」であり、人間のすべての営みは「葬」というコンセプトに集約されると考えます。
カタチにはチカラがあります。カタチとは儀式のことです。わたしは冠婚葬祭会社を経営していますが、冠婚葬祭ほど凄いものはないと痛感することが多いです。というのも、冠婚葬祭というものがなかったら、人類はとうの昔に滅亡していたのではないかと思うのです。
わが社の社名である「サンレー」には「産霊(むすび)」という意味があります。神道と関わりの深い言葉ですが、新郎新婦という2つの「いのち」の結びつきによって、子供という新しい「いのち」を産むということです。「むすび」によって生まれるものこそ、「むすこ」であり、「むすめ」です。結婚式の存在によって、人類は綿々と続いてきたと言ってよいでしょう。
最期のセレモニーである葬儀は、故人の魂を送ることはもちろんですが、残された人々の魂にもエネルギーを与えてくれます。もし葬儀を行われなければ、配偶者や子供など大切な家族の死によって遺族の心には大きな穴が開き、おそらくは自殺の連鎖が起きたことでしょう。葬儀という営みをやめれば、人が人でなくなります。葬儀というカタチは人類の滅亡を防ぐ知恵なのです。
オウム真理教の「麻原彰晃」こと松本智津夫が説法において好んで繰り返した言葉は、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という文句でした。死の事実を露骨に突きつけることによってオウムは多くの信者を獲得しましたが、結局は「人の死をどのように弔うか」という宗教の核心を衝くことはできませんでした。
言うまでもありませんが、人が死ぬのは当たり前です。
「必ず死ぬ」とか「絶対死ぬ」とか「死は避けられない」など、ことさら言う必要なし。最も重要なのは、人が死ぬことではなく、死者をどのように弔うかということなのです。
問われるべきは「死」でなく「葬」なのです。
そして、「葬」とは死者と生者との豊かな関係性を指します。
よって、わたしは『唯死論』ではなく、『唯葬論』という書名の本を書きました。
同書の「宇宙論」からはじまって「葬儀論」へと至る章立ては、2012年に逝去した偉大な思想家である吉本隆明氏の名著『共同幻想論』(角川文庫ソフィア)をイメージしました。同書は、その後の唯幻論や唯脳論の母体ともなった画期的な書物でした。不遜を承知で言えば、わたしは『唯葬論』を『共同幻想論』へのアンサーブックとして書きました。
以前、わたしは『魂をデザインする』(国書刊行会)という本で、2013年に逝去した文化人類学者の山口昌男氏と対談したことがあります。その時、山口氏は「葬式は無駄なこと。しかし、人類は無駄をなくすことはないよ」と言われました。弔いをやめれば人が人でなくなるのです。葬儀というカタチは人類の滅亡を防ぐ知恵なのです。吉本氏や山口氏をはじめ、『唯葬論』は多くの死者たちのサポートによって書かれました。同書を書きながら、わたしは「生者は死者によって支えられている」と改めて痛感しました。
未知の超高齢社会を迎える今、万人が「老いる覚悟」と「死ぬ覚悟」を持つことが求められます。そのためには「生者と死者との豊かな関係」が不可欠であり、「人生の卒業式」としての葬儀に対する前向きなイメージと姿勢が重要となります。葬儀を行うことをやめれば、わたしたちは自身の未来をも放棄することになるのではないでしょうか。
葬儀は人類にとっての最重要問題なのです。